
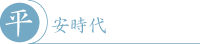 |
| 中世になって日本は、源平の争い(1180)から北条・足利の盛衰を経て秀吉の天下統一(1586)に至るまでの400年間、武家は覇権を賭けて戦さに明け暮れ、日本全土に戦火の絶える間がなかった。武士は忠義を信条としなければ、首が繋がっていなかったであろうし、民百姓は念仏を唱えて後生を願うしか仕方のない時代であった。栄西、道元の禅宗や、法然、親鸞の念仏宗が興って人々に心の在り所を与えていたのも、その時代なればこそのことであろう。 |
 |
中世の日本の医学は、草根木皮の漢方や、僧医の加持祈祷が古代から格別の発展もないままひき継がれていた状態であった。
それに反し西欧では、ギリシャ医学の最高峰ヒポクラテス(BC460〜370)が体液説を唱え、病気を科学的に捉えて、医療は魔法でない事を既に教えていた。アレキサンドリア医学の双璧ヘロヒロス(BC335〜280)とエラシストラス(BC310〜250)は、人体解剖を行って動脈と静脈、知覚神経と運動神経の違いや、神経系のセンターが大脳にあること、心臓の弁膜は血液の逆流を防ぐ装置であること等を知っていた。
ローマでは、ガレヌス(130〜200)が生理学の実験を行い、反回神経の切断や、脊髄をいろいろの高さで切ったり、大脳や小脳に傷をつけたりしてその結果何が起るのかの実験に挑んでいた。そしてこれらの西洋医学の知識は、中世の終りの室町時代(1392〜1573)の後半になって漸く日本に届く機会が訪れた。
|
 (目次) (目次) |
 |

|